異なるジャンルのクリエーションに関わる3人が審査し、3つの個展の中で、資生堂ギャラリーの空間に果敢に挑み、新しい価値の創造を最も感じさせた展覧会にshiseido art egg賞を贈ります。
第18回 shiseido art egg賞
第18回 shiseido art egg賞は、すずえり(鈴木 英倫子)氏に決定いたしました。

すずえり展「Any girl can be glamorous」

すずえり展「Any girl can be glamorous」
2025年7 月29 日には授賞式を行い、当社、梶浦 砂織アート&ヘリテージマネジメント部長(左)より、すずえり氏にトロフィー並びに賞金 20 万円を贈りました。

梶浦 砂織アート&ヘリテージマネジメント部長(左)とすずえり氏(右)

カリモク家具とのコラボレーショントロフィー
受賞の言葉
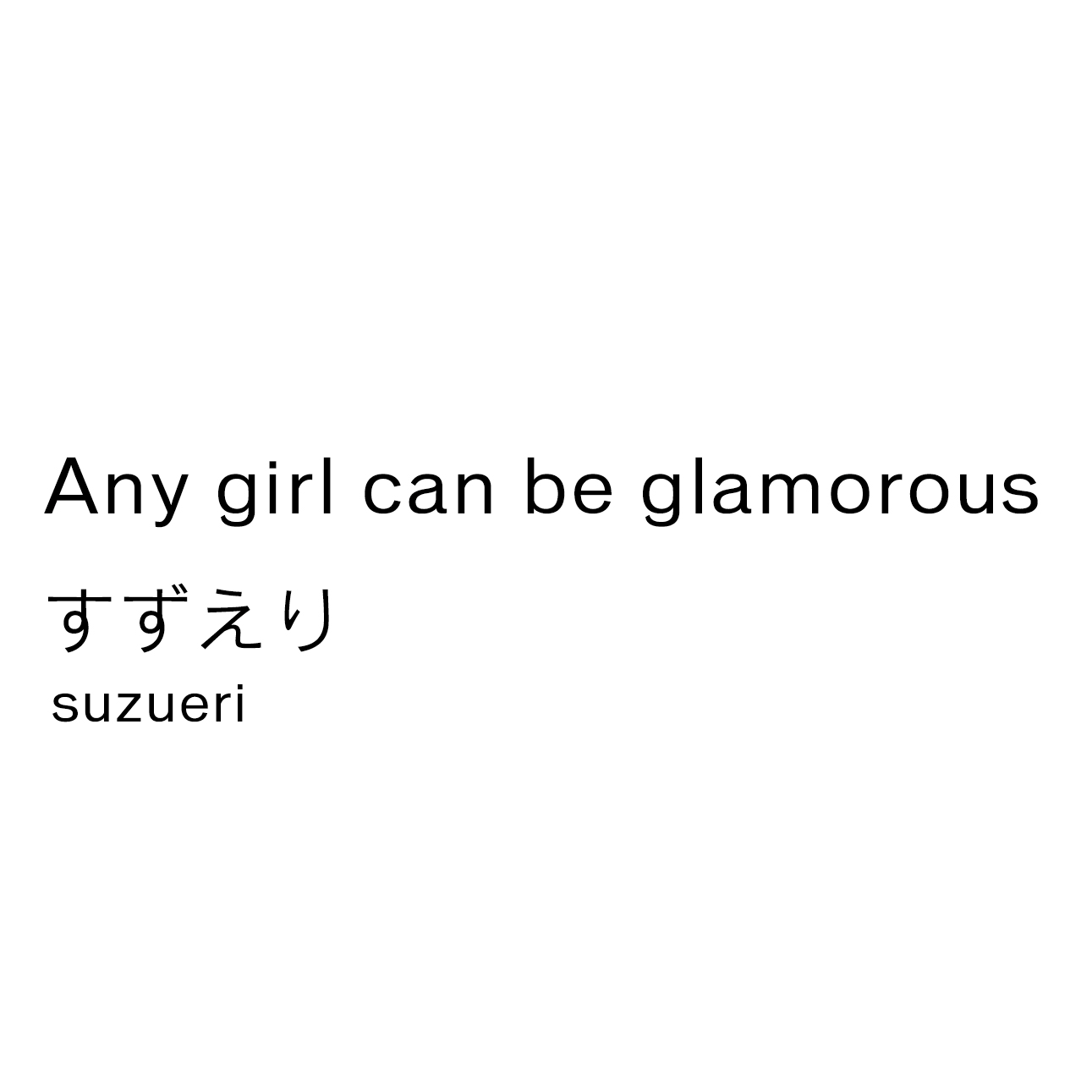
このたびは貴重な賞をありがとうございます。
入選者 3 名それぞれ全く違う作品で、誰が賞をとってもおかしくなかったと思います。並走いただいたキュレーターを始め、ギャラリーや設営、照明のかたがた、自分の身のまわりで手伝ってくれた人々、パフォーマーの 2 人、そしていらした方すべての人々の力で実現した展示です。
自分がいままで経験し、できることすべてを反映させたつもりですが、今のタイミングでこの規模での作品を作る機会をいただけたことを感謝しています。ますます困難な社会となっていますが、今回見えてきた軸のようなものをぶれずに抱えて、先に進んでいきたいとおもいます。
審査総評
本年の審査員は永山 祐子、星野 太、村山 悟郎の3氏が務めました。審査員はshiseido art egg展の内覧会及び開催期間中に各展示を鑑賞し、作家との対話やポートフォリオの精査を経て審査にのぞみました。
見知らぬ過疎地や住宅地でひとりで「盆踊り」を踊り、そこに佇む気配を読み取りモノクロの画面に定着させた大東 忍、ハリウッド女優であり発明家でもあったヘディ・ラマーの生涯をモチーフに、通信と社会の関係や女性の生き方について問いを投げかけたすずえり、デジタルテクノロジーが急速に進化し仮想化が進む現代において、身体や存在をめぐる問いに向き合った平田 尚也。各人のバックグラウンドが絵画、インスタレーション/サウンドアート、彫刻と異なることもあり、表現手法はそれぞれ異なったにもかかわらず、大東による風景の“供養”、すずえりによる過去の実在人物の人生への照射、平田による存在とアウラの探究と、いずれも “魂” ともいうべきものを主題としていた点に共通性が見られました。
3者とも空間を精緻に読みとり、その特性をうまく生かしたストーリー性のある展示を展開していました。いずれも高いクォリティを示していた中で、審査は「展覧会としての完成度の高さ」という主たる原則のもと、作品世界の間口の広さや、鑑賞者の想像力や思考を喚起する力なども加味しながら進められました。
このうち完成度の高さにおいては、木炭画は魅力的で強い存在感があったものの、映像作品にもう一歩の練度が求められた大東、造形感覚や物質的な質感の表現には感覚の鋭さが見られたが、複数の技術の扱いが整理しきれていなかった平田に対し、一人の人物の生涯をめぐる多様で複雑な要素を、破綻させることなく美しいインスタレーションとして仕立て上げたすずえりが一歩抜き出ていました。
この非常に高い完成度を評価し、第18回shiseido art egg賞はすずえりに決定しました。
貴重なお時間をshiseido art egg賞審査に費やし、多角的な視点から議論を重ねてくださった永山 祐子氏、星野 太氏、村山 悟郎氏に心から御礼申し上げます。


審査員所感
大東 忍展 「不寝の夜」
“風景を供養する”をテーマに、過疎地や住宅街の夜の風景を木炭で描いた絵画に加え、映像および、初挑戦した写真も並べた。大展示室は、天井の高さを活かして大小の木炭画をランダムに配置し、作品が浮き出て見えるような照明を施した。小展示室では夕暮れから夜明けにかけての風景の中に発光する自身の身体を置いた映像と、闇の中に光の球を配した写真を展示した。
誰もいない土地で一人で盆踊りを踊り、そこで読みとった気配を描くという、絵に身体性を直接的に介入させる手法は非常にユニークであるし、今後ますます縮小均衡に向かってゆく社会状況を反映した、非常にアクチュアルな表現ともいえるだろう。
絵画作品は素材と表現がよく合致しており、木炭の微細な粒子まで感じさせる質感は、鑑賞者に強く迫ってくる力がある。深い黒の中に浮かび上がる光が描かれた作品群は、それらが生み出す空気感も含めて圧巻であった。過疎地の暗い風景を、都会にあるホワイトキューブの空間に展示するという極端な対比は何らかの含意を感じさせるところがあり、作品のランダムな配置は鑑賞者に身体的なリズムをもたらす効果があった。ただ、このリズムを絵画的な近景・中景・遠景といった視覚の前後運動までをも含んだものとするための表現として、茂みなど近景を描いた木炭の細密描画は、やや苦戦していたように感じられた。
写真作品は、より深みのある黒を発色するため和紙にプリントされている。その狙いは果たされているものの、絵画に比べてやや印象が薄い。より目指す表現に近づくには、ピンホールカメラ等を用いることも考えられたかもしれない。
映像作品も木炭画の強度には及ばなかった。今回、大東は木炭というメディウムにこだわらず、あえて多様な手法に挑戦したという。今後の長い制作活動を考えるとその挑戦は必要だが、木炭による表現を突き詰めた方が、より大きな突破力となったのではないかと考えられる。突き詰めた先にはおそらく、よりスケールの大きな、高い普遍性をもった絵画が生まれてくるだろう。将来が楽しみな作家である。


すずえり展 「Any girl can be glamorous」
通信技術と、その歴史において重要な発明をもたらした女優ヘディ・ラマーの人生をテーマにした、リサーチに基づくインスタレーション。大展示室に吊るされた多数の電球には、ラマーの語る声や出演映画の音声、共同発明者の作曲した音源などが光の波に変換されて仕込まれており、受信機を近づけることで音声が再生される仕掛けである。
小展示室には、踊り場のトイピアノとBluetoothで接続されたアップライトピアノが置かれた。ラマーの朗読する詩に対応してトイピアノが鳴らされると、階下のピアノも連動して演奏されるという、通信技術に焦点を当てた展示だった。
使用される技術そのものをテーマとした表現手法や、細部にわたって高精度に練られた構成など、完成度は非常に高い。鑑賞者が受信機をかざす姿も作品の一部として取り込まれるなど、鑑賞者を巻き込む力も大きかった。
リサーチに基づいた内容とその表現形式には必然性があり、フェミニズムの問題に通じるトピックの織り込み方も巧みである。実在した女優を扱いながら彼女の技術開発の側面に焦点を当て、ビジュアルインパクトを追わない抑制的な構成や、SNSでの積極的な発信を避けた姿勢などに、ラマーへのリスペクトと、故人をモチーフにすることへの徹底的な配慮を感じた。こういった倫理性は重要である。
全体によく考えられ、どの断面をとっても高い整合性が見られる洗練された展示となっていた。整いすぎて“腑に落ち”すぎ、もう少し余白があってもよいとさえ感じさせ、もう一段強固な芯がほしいところもあった。また、現代美術というジャンルに閉じた印象もあるが、公募展のレベルを凌駕する洗練度であることに変わりはなく、この質の高さにより、第18回shiseido art egg賞はすずえりに決定した。
懸念点として、電球を配した空間がボルタンスキー作品を想起させることがある。通信技術や音声を介在させている点でアプローチは全く異なり、技術とテーマに強い必然性もあるため、さほど問題視する必要はないだろうが、写真で記録した場合の視覚的な類似性については一考が必要と考えられる。


平田 尚也展 「仮現の反射/Reflections of Bric-a-Brac」
インターネット上に漂う3Dデータや画像を収集し、それらの素材を重ね合わせて改変・構成した映像作品と、同様の手法で収集したデータを3Dプリンタなどの手段で出力した立体や平面作品による、カラフルでビジュアルインパクトの強い展示である。そのインパクトは、独特の質感をもつ映像を壁面全体に大きく投影し、大音量で見せるという手法にも支えられている。個々の作品は自立しつつも、互いにゆるやかにネットワークを形成しているという点でも、巧みな展示構成といえる。
VR、モーションキャプチャー、生成AI、3Dモデリングと流体シミュレーションと、多様なデジタルテクノロジーを混在させて制作された作品群は、現在のテクノロジー環境の記録とも見える。作家自身、V Rチャットを日常的に使用し、仮想世界でのアバターを通して存在のあり方を認識しようとしているという。デジタル空間における新たなリアリティやアウラの出現条件を探る作品は、こうした作家の意識に裏打ちされている。
その意識が作品そのものにより鮮明に現れていれば、説得力はいっそう増しただろう。なお、モーションキャプチャーで踊るアバターと、AIの動画生成によるダンスの運動は、概念的に異なり、とくに身体の個体性・同一性という観点で相反する。それらを映像作品において未分化に併存させていた点は、改めて整理する必要があるだろう。
また、多様な要素を混在させすぎており、タイトルやテーマと、展示そのものが与えるユーモラスな印象との間に落差も感じられた。作品には近未来から現在を見たときのパロディとも思えるコミカルさがあり、平田の個性はむしろこの方向に発揮されている。この落差により向き合うことで、より鑑賞者の共感を得られる作品になるのではないか。
造形感覚に優れ、映像や立体作品にも独特の物質的な質感が表現されており、一つの世界から別の世界が生まれてくるような現代のリアルな感覚も映し出されていた。主題は、今後登場してくる新しいテクノロジーにも広がっていくだろう。造形感覚をベースに表現の整理を進めることで、さらに大きな飛躍が期待される。


審査員

永山 祐子(建築家)
1975年東京生まれ。青木淳建築計画事務所を経て2002年永山祐子建築設計設立。主な仕事に「豊島横尾館」「ドバイ国際博覧会日本館」「東急歌舞伎町タワー」、大阪・関西万博「ウーマンズ パビリオン」と「パナソニックグループパビリオン『ノモの国』」など。JIA新人賞(2014)、山梨県建築文化賞、東京建築賞優秀賞(2018)、照明デザイン賞最優秀賞(2021)、WAF Highly Commended(2022)、IFデザイン賞(2023)など。現在「Torch Tower」などの計画が進行中。

星野 太(美学者)
1983年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科准教授。専門は美学、表象文化論。著書に『崇高と資本主義』(青土社、2024年)、『食客論』(講談社、2023年)、『崇高のリミナリティ』(フィルムアート社、2022年)、『美学のプラクティス』(水声社、2021年)、『崇高の修辞学』(月曜社、2017年)などがある。

村山 悟郎(美術家)
1983年東京生まれ。博士(美術)。東京大学比較文学比較文化研究室特任研究員。絵画を学び、生命システムや科学哲学を理論的背景として、人間の制作行為(ポイエーシス)の時間性や創発性を探求している。代表作「織物絵画」に見られるように、自己組織的なプロセスやパターンを絵画やドローイングを通して表現。近年はAIのパターン認識/生成や、人間の AIに対する感性的理解を探り、表現領域を拡張し続けている。
第18回 shiseido art egg 賞トロフィーについて
日本の木「セン」で制作された世界でひとつのトロフィーです。本トロフィーは、カリモク家具*とのコラボレーションで実現しました。家具製造の過程で出る端材を再利用し、少し変形したようなたまごのフォルムは、社会に柔軟に適応しながら、多くの事を吸収するしなやかさを表現しています。
*カリモク家具:端材や未利用材を活用した製品の開発など、森林資源の有効活用を推進する木製家具メーカー。当社 BAUM ブランドの容器制作もコラボレーションしています。
撮影:加藤 健
記事:桜井 裕子
これまでのshiseido art egg賞の結果は下記よりご覧ください。