資生堂ギャラリーは、1919年のオープン以来「新しい美の発見と創造」という考えのもと、90年以上活動を継続してきました。shiseido art egg (シセイドウ アートエッグ)は、その活動の一環として、新進アーティストの皆さんに、ギャラリーの門戸を広く開く公募制のプログラムです。
9回目を迎える本年は、全国各地より昨年を上回る340件の応募をいただきました。
今回は昨年同様、全体の80%を20代~30代の方の応募が占め、30代の方の応募が半数以上となりました。
ギャラリーの空間を生かした独創的なプランが多く提案されたなかで、食、家、自然という今日揺らぎつつある根源的なテーマに新鮮な切り口でアプローチする川内理香子、飯嶋桃代、狩野哲郎の3名が入選となりました。
第9回 shiseido art egg/審査結果
審査実施報告
審査概要
| 応募受付: | 2014年6月1日~2014年6月15日 |
| 応募総数: | 340件 |
| 審査員: |
岡部 あおみ (美術評論家/資生堂ギャラリーアドバイザー) 水沢 勉 (神奈川県立近代美術館館長/資生堂ギャラリーアドバイザー) 資生堂 企業文化部 |
審査員所感
岡部 あおみ(美術評論家/資生堂ギャラリーアドバイザー)
従来よりも40点近く多い応募があり、まず参加してくださった皆様に心よりお礼を申し上げたい。とても嬉しかったが、審査にはいつもにない疲労を伴った。すでに応募経験のある方々も、より充実したプロポーザルを寄せてくださり、今回こそ取り上げたいと思う魅力的な作品もあった。参加できずに終わった実力派の応募者は、さぞがっかりされたことだろう。何度も新たな提案を考えてくださる努力に頭が下がる。でも諦めずにぜひまた応募してくださることを期待している。
これまであまり出会ったことのない応募作品群に興味をひかれた。その一つが「不可視なもの」への傾倒だ。もちろん、そうした仕事をもともと手掛けてきた人たちの応募が重なったという偶然もあるだろうが、審査に携わった水沢勉氏からも指摘があり、「どこかいつもと違う」と感じたのが私一人ではなかったことがわかった。参加までは至らなかったが、その内の作家の一人は最終審査まで残った。
戦後のアメリカの評論を先導したグリンバーグのフォーマリズムのイデオロギーは、芸術の自立性を主張し、視覚的経験や要素に芸術の価値を限定してきた。先述した「不可視なもの」とは、そうしたモダニズムの流れとは相反する何か、ヴィジュアル・アートの歴史においては、ある意味でタブーに近い位置に置かれてきた要素だ。近年、建築だけではなく美術の分野でも、ルドルフ・シュタイナーの教示や造形物への関心が再燃しているのもこうした意識の表出の中でとらえることができる。今回の応募で言えば、たとえば地霊や幽霊のテーマなどだ。ローカル・ヒストリーを重要視するポスト・モダンな潮流とも関連しているし、日本では若手作家が大学のある都市に限らず、地方の芸術祭などでも幅広く活動するようになり、村に残る伝説や神々の話に遭遇する機会が増えたという状況の変化もあるだろう。さらに3.11以降の見通しのつかない現状や戦争への新たな危機感とともに、濃密な死の隣接と恐怖が拭いがたく知覚され、生に異質な揺らめきと陰翳を授けているように感じられた。
水沢 勉(神奈川県立近代美術館館長/資生堂ギャラリーアドバイザー)
この夏、しばらくポーランドのウッチにいた。三度目の滞在であったが、1991年のソビエト体制崩壊後、この10年間、急速に旧繊維工場群の再利用が始まっていた。あの世界的に名高いウニスムを中心とする1920年代の構成主義以降のコレクションの一部もまた、そうした旧工場のひとつのなかに新しい美術館となって移設されていた。日本でも同じだが、商業施設のなかに組み込まれてしまうと、やや「アート」の存在はどこかくすんでみえる。だからこそ、商業以上に商業的になるという選択も当然戦略としてありえるわけである。しかし、モダン・クラシックという殿堂入りを果たしているウワディワウ・スチェミンスキーやカタジーナ・コブロへの尊敬の思いはむしろ美術館に地道な姿勢を守らせている。しかし、それ以上に、ポーランドにいると隣国ウクライナの情勢はきわめて身近な問題である。途中でよったワルシャワの現代美術センターでは、ウクライナの動乱を記録する生々しい映像作品が会場の入口のすぐそばにスクリーニングされていた。キスをしながら20歳前後の若い男女のカップルがそれを観ていた。
「愛国心は他人の国境を知らない。」(スタニスワフ・イェジ・レツ)
現ウクライナで生まれポーランドで死んだ詩人(1909-1966)の言葉を思いだす(翻訳は沼野充義氏のフェイスブックより)。わたしたちは、いま「他人」をどれほど知っているのであろうか。
資生堂ギャラリーという東京のど真ん中の商業施設のなかにある展示空間。そのなかで若い才能を紹介するアートエッグの審査にあたって、いつでもわたしが望むのは、知らない「他人」の未知の領域、その創造の「国境」である。創造においてその「国境」は多様であり、知り尽くすことはできないという事実ほどわたしを勇気づけるものはない。
入選者
川内理香子
絵画
展覧会会期:2015年1月9日~2015年2月1日
1990 東京生まれ
2014 多摩美術大学美術学部絵画学科油画専攻在籍
資生堂と聞くと資生堂パーラーと資生堂ギャラリーとを思い浮かべることが多いように思います。小さい頃に、よく祖父母に連れられて資生堂パーラーで食事をしていたためです。ギャルソンの方が小さな私にも大人と同じように、丁寧に接してくださったのを覚えています。あれから体は大きくなりましたが、アーティストとしてはまだまだひよっ子です。作家としての体もここから殻を破りどんどん成長させていきたいです。がんばります。


審査員評
岡部 あおみ
何枚見ても見飽きない川内理香子のシンプルなドローイングの魅力はどこから来るのだろう。まだ実物を目にしていないが、湧き出る想像力の泉に惹きこまれる。描く対象は寿司、菓子、野菜、動物、そして人や行為といったありふれた事物にすぎない。なにげないスケッチのようなそっけない描線に着彩がたまにあるだけだが、無意識が踊り出る柔らかな線の流れが絶妙だ。素描を生の営みと一体化する彼女の作品は、アール・ブリュット的と言えるかもしれない。ドローイングで大展示室を埋めたいという川内の今回の提案は、食べ物への強迫観念が強かった彼女の幼児体験を反映しているようで興味深い。24歳の川内はこれまでのarteggの最年少参加者で現在まだ美大在学中。食べ物と彼女の切っても切れない不思議な関係は、人と食材の空想勾配による希少種を育み、食べるという日常の営為にかすかな不安の余韻と近未来的微動を授ける。
水沢 勉
エクササイズとしてのドローイング。自己目的と化した純粋な状態のグラフェイン(線描)。なにかを写すというよりも、自動に生成されてくる印象が、川内の繊細で、フレッシュなドローイングにはいつも備わっている。アンティ・クリマクスの精神。そこには、頂点もなければ、底辺もない。ひたすらに綴られていく。食卓を前にして、壁一面のドローイングを眺めるという発想の展示が提案されている。作者自身、それをそんな風に眺め渡したことは一度もないのではなかろうか。そのとき、ひとつひとつの作品に近づくのではなく、その波動を身に浴びてみたいという意図が感じられる。それは、裏返しにすれば、描くことに没入していることの反証であろう。しかも、それはなにも仰々しい鑑賞ではない。食べることと同じ日常です — そう作者は呟いてみたいのではなかろうか。ささやかな領分、しかし、創造の森への探索のはじまり。
飯嶋桃代
彫刻
展覧会会期:2015年2月6日~2015年3月1日
1982 神奈川生まれ
2011 女子美術大学大学院美術研究科美術専攻博士後期課程修了
この度は、資生堂ギャラリーという美しい空間で展示できる機会を頂き光栄に思っています。わたしは、これまで家族の記憶をテーマに制作を続けて来ました。家族が日々の営みのなかで使用した食器や衣服などを用いた作品です。これらの事物には、家族の記憶が使用の痕跡となって現れています。痕跡が宿す記憶が声なき声となって、ギャラリーの空間と共鳴することを願っています。


撮影:末正真礼生
審査員評
岡部 あおみ
収集、凝固、切断、造形と何重にも手が込んだプロセスを踏む飯嶋桃代の立体は、最終的にもっとも簡明な形へと落とし込まれる。それが「イエ」だ。たしかにホームレスの方々は家族から切り離された人が多いから、「イエ」が家族を意味してもおかしくはない。だが毎日ワイシャツを着る男性で家族のいない単身者が増え続けている今日では、「イエ」を家族の表徴と規定するのはやや強引かもしれない。一方、現代都市では屋根のある一戸建ての家に家族とともに住む人の数が増加してるようには思えない。これらの「イエ」は飯嶋にとって過去の記憶なのだろうか、未来の理想なのだろうか。透明なパラフィン・ワックスからのぞける古食器などの内部空間からタイトルの「開封」という言葉が導きだされたとしても、彼女がどのような思いをタイトルや作品に込めたのかは実物や展示を見るまでわからない。近年、多くの国々で大きく変わりつつある家や家族の概念を遡上にのせる作品である。
水沢 勉
記憶と彫刻のアマルガムを作りだそうという意志が漲っている才能である。テーマには「家 Home」を掲げ、「衣食住」を、散在状態のインスタレーションではなく、あくまでも彫刻として表現しようとする。今回の提案は、実際に使用された衣服、食器をパラフィンに封じ込め、それを家形に切り出して、ギャラリー空間に設置するという構想である。コロンビア出身の女性彫刻家ドリス・サルセドにもどこか通じる手法であるが、飯嶋は、戦乱や亡命という傷の記憶ではなく、日常のなかに摩耗し、消え去っていくはずの無数の無名の生のあり方を暗示させ、造形化しようとしているようにみえる。家形に切り出されることは断片化にほかならず、その切断の鮮やかさが、わたしたちの対象化しにくいあいまいな時空をいったんエポケーさせる。彫刻としての状態に執着することによって、「わたし」の領域が、造形の断片として、普遍へと転じる可能性に賭けているように思える。
狩野哲郎
インスタレーション
展覧会会期:2015年3月6日~2015年3月29日
1980 宮城生まれ
2007 東京造形大学大学院造形研究科造形専攻修士課程修了
知らないものが目の前にあらわれたとき「純粋な標識」として知覚、認識をすることは人間以外の動物たちにはごく日常的に行われている。理想的な自然ではない環境の中で自由に振る舞う鳥の姿を目にす れば、複数の世界認識が存在することを何度でも思い出す。考えることさえやめなければ、想像しなおすことができる。繰り返し眺めた白い、白い部屋についてさえも。


撮影:森田兼次
Courtesy of the artist and YUKA TSURUNO GALLERY
審査員評
岡部 あおみ
2005、06年なので狩野哲郎はまだ大学在学中だったに違いない。横浜にあった北仲ホワイトのアートスペースで小さな草を生やす彼の個展を見る機会があった。光と静けさに満ちたそのときの感動は、奇をてらってギャラリーで植物を生育する行為とは異なる真摯な姿勢を伝えていた。世界と芸術をまなざす独特な態度は次第に「自然の設計」という理論に結晶し、インスタレーションで使用されたモノ達はその後日常へと戻される。狩野が地下にゴミの山を隠すモエレ沼公園に惹かれるのは、自然と都市を融合した作者イサム・ノグチへの共感と、ノグチが鷹の目をした生来の狩猟者・越境者だったからに違いない。とはいえ閉ざされたアートの場に生命体を滑り込ませる手法は、常に既存のルールを狂わせる。その介入の提案は境界を見据えたチャレンジなので、展示担当者を惑わすのである。銀座の地下で鳥を放つという今回の案は本当に実現可能なのだろうか。
水沢 勉
自然物と人工物の関係をいったん解きほぐし、まったく別の関係の可能性を垣間見せるインスタレーションを試みる。人間の認識は、既存の無数のフレームで雁字搦めにされていることを、狩野の作品はわたしたちに意識させる。そのためには一見かなり特殊と思われる前提を空間に課すことになる。今回は、「ある小鳥が認識しうる「自然」の中から理想のとまり木を探し出すとせよ。」という条件(お題)があり、「自然の設計」と展覧会は題される予定。自然物と人工物には、ほんとうのところ、はっきりと境界はあるのであろうか。「鳥」の感覚を前提としたとき、わたしたちは、それに疑いを抱くことになるはずだ。そのあいまいな領域にこそ、未知のアートが自生する可能性がある。狩野は、洗練された手つきで「美しい」インスタレーションが作れてしまうが、その意図は、大きな射程を備えている。地下のギャラリーが、ケージ(鳥小屋)となり、また、類比的に自然への通路となる。
応募状況
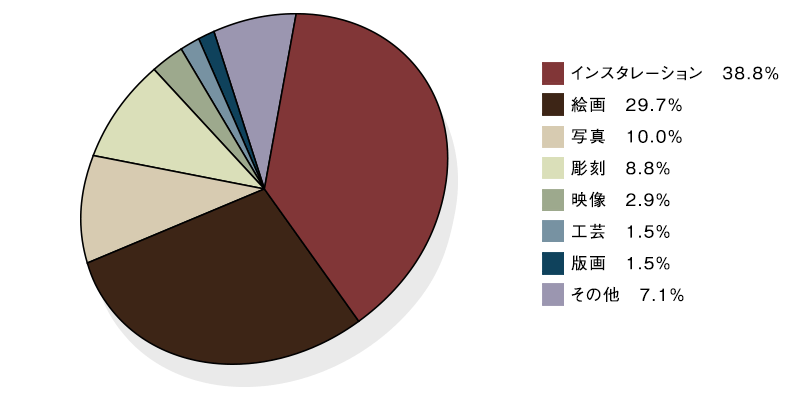
これまでのshiseido art eggの審査結果は下記よりご覧ください。